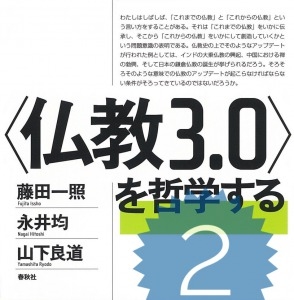- 話者:柳田敏洋(イエズス会司祭・イエズス会霊性センター「せせらぎ」所長)
- 日時:2018年4月14日
- 場所:2018(平成30)年 青空の黙想リトリート in 上石神井黙想の家
- 出典(音声ファイル):18/04/14柳田敏洋神父の講話 『私たちはどこへ向かうのか?』 | 一法庵(20分50秒頃から)
- [ ]内は、文意を明瞭にするために、当サイトの管理人が補足した文字です。
(柳田敏洋神父の講話『私たちはどこへ向かうのか?』(1 of 2)からの続き)
今回も、この青空リトリートが初めての方は結構、「もう疲れる」、「しんどい」、「脚が痛くてたまらないのに、まだどれだけ我慢しなければいけないの?」とかですね、そういうふうな実感を持っておられる方があるかと思います。私も11年前にインドで初めて[ゴエンカ式のヴィパッサナー瞑想の]10日間の体験をした時に、やっぱり同じように感じました。「わざわざ航空運賃を払って来たのに、こんな所でくじけちゃ元も子もない」というような打算的な思いもあったので。
最初はどうするかというと、「頑張る、我慢する、我慢する、耐える、耐える、耐えぬく」ということですね。チーンという鐘が鳴るのが待ち遠しくてたまらない。こういう感じですね。で、まあ、それで何とか何とか乗り切っていくのですが。でも、山下良道さんが、ヴィパッサナ―、マインドフルネス瞑想のポイントとしてお話し下さっているように、アドバイスは常にですね、「どのような痛みが来ても『観察せよ、観察せよ』。“observe, observe”」。そういうふうな言葉をですね、アドバイスとして何度も話されました。
ですから、我慢というのは、「痛くて苦しくてたまらない」ということですよね。やはりここにまた、エゴのからくりがあると思うんですが。まあエゴは、好ましいものを自分に引き寄せて、それと一つになって、うっとりとした満足感に浸りたい。[そして、エゴにとって]好ましくないものは、常に避けて自分から遠ざけようとする厄介なもの。というふうなことですね。
長く座っていると痛みが湧いてきて、その痛みはとんでもない苦しみを私に与えることになります。そうなるとですね、「もう痛い、痛い」というふうな感じになってくると、痛みというネガティブな感覚と自分を一つにしちゃう。このエゴの本質というのは「同化」……自分と何かを、ついつい一つにしちゃう。これは英語でassimilationと言ったりしますが。やっぱりここに、私たちの厄介なエゴの本質があるんじゃないかということですね。
つまり、「本当は自分ではないもの」と自分が、無意識のうちに一つになることで、それを私だと思い込んじゃう。ですから、うっとりするような良いものだったら……「本当に待ち遠しくてたまらなかったルイ・ヴィトンの春物バッグを手に入れた!」……こういうふうな、恍惚感。それは別に、ルイ・ヴィトンのバッグは「私」ではないんだけれど、[それを]手に入れた「私」は、このルイ・ヴィトンの春物最新流行のバッグは「私の存在の一部」のように心理的に感じちゃうと思うんですね。そうなると、うっとりするんですけども、でもそれは全く一時的な儚いものだということですね。
まあ、ポジティブなほうはまだ良いかもしれないんですけど、ネガティブなものは、やっぱり凄く厄介ということですね。その一つが痛みというふうに言っていいと思うのですが。そういったものと、ついつい、エゴは一つになっちゃう。そうしたら、「もう大変だ!」ということになると、エゴは力でそれをやっつけようとします。[その]一つがですね、避けることができないものだったら我慢するとか、別のことを考えて蓋をするとか。こういうふうな形になります。でも結局、痛い厄介なものは残ったままですから、いつまで経っても、真の問題は解決されないということです。
それに対して、「観察しなさい、観察しなさい」……つまり、「ついつい巻き込まれそうになるんだけれども、できるだけ心を穏やかにして、その痛みと、感じられる感覚を現象として見つめなさい。現象として見つめなさい」……こういうふうなアドバイスがあって。まあもちろん、そんな簡単にはできないんですけれども。私の場合は6日目だったんですが、結構激しい脚の痛みがあるのに、ふと気がつくと、心が巻き込まれずに、心臓もバクバクしたりせずに、全く穏やかな心で、自分の痛みを見つめている。こういうふうな境地を体験致しました。
その時に感じたのが、「私の意識というのはこんなにも自由なのか」ということですね。それまではとにかく「我慢、我慢。早く鐘が鳴らないか」……そればっかりを考えるとか、「この痛みがもっと強くなっていったらどうしよう」とか、「医者に[かからなければいけなくなったら]どうしよう」とか、ネガティブな発想がどんどん膨らんで、それが私の痛みを、また心理的に大きくするとか、まあこういったカラクリだったということが後で分かるようになったんですが。やっぱりその6日目の午後の体験、自分の身体の一部の脚に、実際の身体的な痛みがあるのに、心は穏やかにそれを見つめている。こういうふうな境地ですね。ですから、こういった体験をして、そして「本当の私の意識というのは、もっともっと実は自由なんだ」というふうなことを知るようになって、これが私の、一つの乗り越えるきっかけになったと思います。
つまり、そこでですね、私は今までは、「自分はエゴだ」というふうに思っていたけれど、「エゴではないもう一人の私がいる」という気づきですね。つまり、もう一人の私というのは、「痛い、痛い、痛い。大変だ。何とかしなければ。早く終わらないかな。どんなふうにして我慢できるだろうか」とかというふうに右往左往している、そのようなエゴから離れて、静かにその右往左往しているエゴと身体的な強い痛みを見つめている。そういう意識が確かに現れるということですね。そして、そこにこそ本当のこの私があるんじゃないかということですね。これを、まあ私なりに整理をしていって、「根源意識」というふうな名前で、今は呼んでいます。つまり――この「根源意識」というのは、勝手に私が名づけているものですけれども――、あらゆるものに対して巻き込まれない心で、穏やかにその現象を見つめられる。感覚にしても、感情にしても、あるいは思考にしても、ということですね。
私たちが巻き込まれやすいものの一つが、ネガティブな感情だと思いますけれども。誰かの一言でカチンと来て怒りが湧いてくるという時に、ついつい私たちは、エゴの傾向だったら、怒りと自分を一つにして、怒りの雲に自分が飲み込まれて、怒りの中に自分を見失っちゃう。こういったことが時々あったりします。いわゆる、キレるということですね。そうなると、怒りの雲がですね、大きくなって爆発しちゃう。大変なことを起こしちゃうということですね。
それに対して、怒りの雲から離れて、それを静かに「青空」から観る。これが良道さんの「本当の私は青空だ」というふうなところと繋がってくる、というふうなことかなと思いますけれども。「相手の一言で怒りが湧いてきてる」とか、あるいは考えにしてもですね、「あの人は私のことを見下している」というふうに、何か相手に対するレッテルを貼っちゃって、そのレッテルが強いものになると、その「相手は私を見下している」という考えが、「私」のアイデンティティの一部になっちゃう。これはもう、恐ろしいことですね。どんなに相手が優しい言葉をかけてきても、「何か裏があるに違いない」とかですね、もう常にネガティブなフィルターを通した解釈しかできなくなっちゃう。これがまた苦しみを生むということかなと思います。
それに対して、痛みの場合と同じように、「あ、相手の一言で、今、怒りが私の心に沸いてきている。相手の今言ったことで、『あの人は私を見下している』と今思った」というふうに気づく。そして、「価値観を入れないで」ということですから、怒りを裁かない。やっつけようとしない。「厄介なものだ」というふうなネガティブな判断も持ち込まない。相手にレッテルを貼る考えに対しても。こういうふうなところを見ていくとですね、「あ、これはイエスが言っている『存在の無条件の肯定』と全く同じだ」。
つまり、私の心に沸いてくる怒りに対しても、あるいは、相手をネガティブに決めつけるレッテル貼りの考えを持っても、「それを取り除こう」と今まではエゴがしていた。でも、そうではない。イエスが教えているアガペとは、どんなにネガティブなものが私の心に現れてきても、あるがままの存在、心に表れた存在の一つとして、それを認め、その存在を受けとめていくということ。ここに、イエスが教える本当の大切なアガペの中味があるということに、だんだんだんだんと気づき始めました。
そうして、そのように、あらゆるネガティブな心の状態をも、あるがままに、巻き込まれない形で気づいて、そしてその存在を認めていくというあり方がアガペであって、そのような気づきが出来るところにこそ、本当の私がある。ということが、だんだんと分かってきました。そして、このような無償・無条件の気づきの営みを「根源意識」というふうに名づけているのですが、この根源意識の場こそ本当の私の場だ。瞑想は、この根源意識と名付けた「本当の私」という場所に目覚めて、そこに本当の自分を見出していくという、こういうふうな営みではないか、というふうに感じるようになりました。
そこで、また私にとって非常に大切なのは、これが神とどう関係するかということですね。まあ、聖書の中にもいろいろあるんですが、いわゆるキリスト教の神様というのは天におられるとかですね……例えば子供向きのキリスト教についての絵本とかだったら、神様は「雲の上から、白いひげを生やしたおじいさんが地上を眺めている」とかですね、そういうふうに「外なる神」だというふうにイメージしやすいのですが、本当はそうではなくて、例えばパウロという人は「あなた方は知らないのですか。あなたがたは、神の神殿であることを。神は、私たちの内に住まわれる」とか、あるいはイエスの教えや生涯について書き記した[4つの]福音書というものがあるんですが、その中の1つの「ヨハネ福音書」では「父と私はあなた方のところに行って住む」……こういうふうな、非常に深い言葉があります。
つまり、神とは私の中に住まわれる神だ。そして、特に聖霊の働きということが、キリスト教では人間との関わりで強調されるんですが、この内なる聖霊の働きが、私の意識の根源に及んでいるから、私は自分の気づきとして、自分の心に沸いてくるネガティブな感覚や感情や思考を、全くあるがままに、一切価値判断を入れず、裁いたりせずに、存在肯定し、存在を受けとめていくことができる。
キリスト教の中での大きな問題に「人間の自由と、その神の恵みをどう調和させるか」というふうなことがあるんですが、それが全くすんなりとストンと落ちるということです。つまり、私が確かに自分で気づいている。私の力によって。でも同時に、それは私の意識の根源に働く愛の神の働きに協力する形での、私の営みだ。
そうしたら、ここには、何でもかんでも自力でこの世の問題を解決していこうとする人間万能中心主義でもないし、また、宗教の中にもおかしなこととしてあるのが「あらゆるものを全く神に丸投げ……『もう私には何もできません。あなただけが頼りです』」という丸投げ型に、神に頼っちゃう。これもやっぱりおかしなこと。ということです。
ですから、ここには非常に深い――「神秘的」というふうに言えるかも分かりませんが――人間の神に対する協力ということの中に、本当の宗教心というふうなものがあると思いますし、その一つの現れが――キリスト教の枠の中で[の表現]ということになりますが――ヴィパッサナーをしている時の私を、このように営ませてくれているのは、神の恵みの働きが確かに私の意識の根底に働いているから。こういうふうに理解をすることができるということですね。そして、こういうふうなところでこそ、神との出会いの場があるということですね。そして、そこにこそ本当の私の場がある。
つまり、この瞑想、本当にキリスト教にとっても素晴らしいなあと思うのは――やはりキリスト教の人も「本当の私」というふうなことについて求め、そしてエゴの中に彷徨っているというふうなことかと思いますが――、真の私とは、私が神と出会う場である。そしてそれは、まさに「無償・無条件の存在肯定」というイエスが示したアガペを生きる場にある。全部重なってくるということですね。ここ、すごく大切な点かなあというふうに思います。
そこでですね、それを教えてくれるのが、身体なんですね。で、これ本当にヴィパッサナーの素晴らしいところ、あるいは禅もそうだと思いますけれども、東洋の瞑想というのは身体を大切にします。身体から瞑想に入っていきます。
キリスト教の伝統[の中に、身体を扱うことが]無いことはないんですが、[キリスト教では]基本的には心と知性で祈る、神に向かう。そういうふうなパターンで、身体は二の次とかですね……。やっぱりここに、歴史的に見るならば――皆さんも聞かれた事があるかと思いますが――ギリシャの哲学を始めた人と言われているプラトンというのは、「肉体は魂の牢獄である。人間の救済とは、その魂が、牢獄になっている肉体から解放されることだ」というふうに考えていて、これがキリスト教の教えの中にも相当浸透していました。ですから、やはりキリスト教の中でですね、身体は二の次とかですね、肉欲とかいう言う方があったりするんですよ。本当は心と頭の問題なのに、あたかも身体自身が勝手に欲するとかですね、欲望を持つとか、まあそういうふうなイメージを、キリスト教の人間観の中に植え付けたところがあります。
でも、そうではない。全く逆ですね。一切、身体には欲が無いということですね。これも、瞑想を通して学んでいきました。実は[ヴィパッサナー瞑想を実践するより]前に、インドでヨーガに出会ってですね、ヨーガの素晴らしさというようなことを私は感じるようになったんですが、やっぱりそれはですね、身体の素晴らしさに開眼することができたということです。
つまり、キリスト教の枠の中で言っていきますとですね、「頭と心が求めてやまない神を、すでに身体は発見し、生きている」ということ。神と結び合って生きているという現実を「神の国」というふうにキリスト教で言ったりしますが、身体は既に「神の国」を生きているということですね。つまり、「身体の一つ一つの部分はアガペを生きている。無償・無条件の愛、無償・無条件の存在肯定を生きている」……こんなふうに言うことができるのじゃないか。
例えば、心臓。心臓は血液を体中に送り込むというポンプの役割を果たしますが、それを通して酸素というエネルギーを身体の隅々にまで送ります。それで私が生きるということですよね。でも、心臓は全くそれを無償・無条件で行っているということです。心臓は私たちがこの世に生まれ落ちた時から働き続けています。私たちは今晩、瞑想した後、部屋で寝ると思いますけど、心臓は寝ません。[心臓が]「私も休ませてもらいます」と言ったら、私の朝の目覚めは無しというふうになるんで(笑)。私たちが疲れて休んでいる時にも、心臓は働いている、働いている、働いている。つまり、この世をおさらばする時まで、心臓は休みなく働き続ける。 でも、こんなにずっと、私が生まれ落ちてきてから働き続けている心臓なんだけども、じゃあ「はい、一年にこれだけ血液を送ったから、リッターいくらで請求します」とか、そういったことを心臓は要求しない。あるいは、「こんなに頑張っている私を認めて、感謝の一言ぐらい言って欲しい」とか、こういうふうなことも一切言わないということですね。あるいは、全く無条件というのはですね、「こんな酷い人じゃなくて、もっと立派な人の心臓になりたかった」[というような]選り好みを心臓はしない。
全く無条件で、その人がどんなエゴにまみれている人であろうと、どんな立派な人であろうと、その人を無条件に受けとめて、その人を生かそう、生かそうとする。そして、このアガペの愛のシンボルである心臓の素晴らしさにだんだんと気づくようになったんですが、真の愛は自らを隠すんです。つまり、正常であって調子が良ければ良いほど、その姿に私たちは気づかない。その営みに気づかない。問題が起こった時にだけ気づくんです。病気とか、何かの欠陥がある[というふうに]。ですから、それは心臓だけじゃなくて、あらゆる部分について言うことが出来ます。肺、胃、腸、肝臓、腎臓、あるいは筋肉。あらゆるものがアガペなんです。無償・無条件の愛を生きている。そして、それが正常であればあるほど、自らを隠すということですね。
例えば、イエスは偽善者の施しについて批判をしながら、「あなた方は、右手がすることを左手に知らせてはならない」……こんなふうな言葉をイエスは言っています。右手のすることを左手も知らないというのは、全くの、自らを隠す。つまり、「わたくし」が無いんです。真のアガペには「わたくし」が無い。そして、丁寧に見ていくならば、心臓には「わたくし」はありません。肺にも「わたくし」はありません。これが私たちの身体だ。
そしてさらに、このような心臓や肺、そして胃、腸、あるいは筋肉を構成しているものは、いわゆる細胞ですね。今から5年前に、人間の大人の細胞がどれぐらいかというのが、かなり正確に推測できるようになって、その結果によるならば、私たち一人一人は約37兆の細胞を持っているということですね。そしてその殆どは、一年間で入れ替わるということですね。そして皆さんご存知のように、一つ一つの細胞は、DNAという私たち一人一人の設計図、遺伝子の設計図を全部持っているんだけれども、でも例えば、私の人差し指のこの細胞が、新しい細胞に入れ替わる時に、その人差し指のところとしてだけ働く。あるいは、目の細胞が入れ替わる時にも、目の働きの部分だけが現れてくる。それ以外は一切現れない。つまり、現れる部分に対して、全く自分を調和させて働いて、そして働き終わると、全く人知れず気づかれず、自ら退いていく。無の内に表れて、ふさわしい役目を果たし、無の内に退く。誰も何も気づかないうちに。これこそがアガペ。
ですから、だんだんと分かってくるのは、本当の愛を生きている人は知られない。隠されているんです。そして、知られることを望むというのは、もう既にエゴがあるということ。無理があるということ。真のアガペを生きるときには、知られる・知られないは何の関係もない、何の関心もない。ここに私たちは召されている。アガペの人になるというのは、そういうふうにですね、全く自分というものを無にして、そして相応しい働きをしていく。こういうふうなところに、アガペというふうな場がある。そしてまさに、根源意識というのを見ていったらですね、こういうふうな働きをする場が、根源意識と名付けられているところではないか。そしてここに、私たちにとって本当に大切な真の私の場があるというふうにですね、見ていくことができるのではないかということです。
そこで――またキリスト教の話ばかりになってしまうんですが――、こういうふうな私たちが、神の似姿として造られて、その似姿とは神のアガペである。じゃあ、アガペに似たものとしてアガペを生きるということであるならば、私たちの人間としての完成は、アガペの人になること。つまり、掛け値なしに無償・無条件の愛を生きる人になっていく。無償・無条件の存在肯定を生きる人になっていく。じゃあ、それ、誰ができているんですか? 「イエス・キリストだ」。こういうふうに私たちは信じている。そしてイエス・キリストの中に、この神の似姿を完成された人を見て、そしてその人を手本にして、私たちも歩んでいこう。
じゃあ、このアガペの究極って何ですか? 私たちキリスト教は、3月の末と4月の初めに、キリスト教の暦で一番大切なイースターを迎えました。イエス・キリストの十字架上の死――十字架がここにも架かっていますけれども――と、その三日後の蘇り……これを、一番大きなキリスト教の出来事として私たちは今年も祝いました。つまり、それに何を見ていくか。まあいわゆる、この十字架というふうなものは、ローマがその当時編み出した見せしめ刑ですね。政治犯にだけ適用された処罰刑であって、できるだけ苦しみが長く続くように……つまり、両手足に釘を打ちこんで、そしてその十字架に磔にすることで、すぐには死なないです。苦しみが長く長く続く。というふうなことで、「ローマに逆らうと、こんな酷い苦しみをお前たちは受けることになるんだぞ」というね、見せしめ刑ですね。ですから、まあ私たちが普通に見た時には、まあ特に日本人には、十字架のキリストというのはなかなか馴染めないところがあるというのは、そういう残酷さそのものを見える形で表す、そういうふうなものだから。でも、キリスト教はこれをアガペの愛のシンボルとして見ていきます。
つまり、イエスは――「ヨハネの福音書」の15章で言っておられるのですが――「友のために自分の命を捨てるほど大きなアガペはない」。ですから、相手の必要に応えて無償・無条件の愛を現す[ことも]もちろんアガペなんですが、最終的に最も大きなものは、自分を、そのアガペのために惜しみなく自分の命を差し出していくというところにある。これを、私たちキリスト教は、この十字架のイエスの中に見ていくということですね。ですから、十字架のイエスは、あのような残酷な殺され方をしたけれども、まったくそれに対してアガペを生き抜かれたということです。
とても興味深いのは、この十字架にイエスが架かった時に、十字架に付けた当局の人たちがですね、「お前がもし本当の救い主なら、今すぐ十字架から降りてみろ。他人は救ったのに、自分は救えない。今すぐ降りてみろ。そうしたら信じてやろう」と嘲笑うんですね。でもイエスは十字架から降りない。十字架から降りるというのは、そこで、エゴが、神のエゴが出ることになる。「お前ら見ておれ。どんな酷いことをしたか思い知らせてやる」……これ、恐ろしい裁きの神です。力の神です。キリスト教が信じているのは、神の救いは決して力ではなく、愛だ。アガペのみが人間を救うことができる。この教えですね。イエスは苦しみのうちに十字架上で亡くなられた。
ここにですね、本当に大きなキリスト教の神秘があって……ということなんですが。ここにですね、すごく大切な点があります。そのように亡くなったキリストをですね、「あの人こそが私たちの救い主だ」というふうに信じるグループが現れて、それがキリスト教に繋がっていく、キリスト教の成立ということになっていくんですが。
「このように私たちに神を示してくださったイエス・キリストとは何者か」ということが、非常に大きな問題になります。これについては、いわゆる「キリストとは何者か」ということで、キリスト論という言葉で言われるようになっているんですが。イエスが亡くなったのは、紀元30年4月7日というふうに言われています。それから6世紀、7世紀くらい、つまり600年、700年かけて、この「キリストとは何者か」というふうなことが論じられて、最終的に一つにまとまっていくのですが、それは「イエス・キリストとは、真の神であり、真の人である」[ということ]。つまり「50%神で、50%人である」わけではなく、「100%神であり、かつ100%人[である]」。これがイエス・キリストだ。じゃあ、どんなふうにしてその、イエス・キリストのなかにこの神と人間が居ることができるのか。これがもう、古代の教会の大問題だったんです。でも、ここにですね、私たちがやっている――良道さんも言っている――「二人の私」を解くヒントがあるんですね、はい。つまり、ここでですね、「十字架で苦しんだイエスはどのイエスか?」……こういう問題[が出てくる]。
つまり、100%神なら、神であるイエスが苦しんだのか? あるいは苦しまなかったのか? こういうふうな、非常に、追求していくと大きな問題があるんですけれども。ですから、ここにはですね、最終的に「私というものを構成しているものは一体何か?」という非常に大きな問題が出てきます。実はこの、古代教会の「キリストとは何者か」というふうな、すごい哲学的な、神学的な議論の中にですね、人格という概念が出てくる。
私たちは[人格という言葉を]普通に使っていますけれども。つまり、私は自分のこういうような身体を持っていますけれども、でも私の両手両足がもげても、私は私。外見ではないということですね。まだ髪の毛はありますけど、これが全部無くなっても、私は私です。あるいは、自動車事故に遭って車が燃えて、誰が見ても分からな[いほど身体が損傷しても]、私が鏡を見たら「あ、私の身体が丸焦げになって、もうまったくひどい姿になった」と私は気づける。
つまり、そういう「私」というもの[が]、私たち一人一人にはある。他の誰でもないこの「私」。そういうところに「人格」というのを見ていこうとする。「じゃあ、この『人格』って一体なんですか?」というふうな、そういったことが非常に大きな問題になってきて。それをですね、ギリシャ教父と呼ばれる、ギリシャ語で神学を勉強する人たちは「ヒュポスターシス」という、そういうふうなギリシャ語で言い表すようになりました。これがですね、丁寧に見ていくと、「根源意識」とすごく重なってくるんです。
つまり、「ヒュポスターシス」というギリシャ語は、その人のその人たる中心を表すというふうな概念として成立してくるんですが、それは、実は何ものでもない。何もの[かで]あったら、それは対象化されてしまいます。つまり、真の私というのは、私以外の者を私以外の者だと認める事ができる。そういうふうな私であるならば、「これが私である」というふうに見せることができるとしたら、じゃあ、「これが私であると見せている私は誰ですか? その人は誰ですか?」……こういう問題が出てきます。
というふうに――ちょっと、頭のはたらきということも必要になってくるかも分かりませんが――、こういうふうに見ていくと、真の私が私であるというふうに言い切ることができるものは「無」なんです。そして「無」以外に、私が私であるというところを成り立たせる場はない。これが、神だ。
イエス・キリストは神の子として生まれたというふうに[キリスト教徒は]信じているんですが、それは、肉体を持って人として、神がクリスマスにお生まれになったということを、クリスマスとしてお祝いするんですが、その神の「ヒュポスターシス」――これを位格とか人格とか言ったりするのですが――、その「私性」というのを持って、キリストはマリアの胎内からお生まれになったというふうに理解することができるようになりました。
そうして見ていくとですね、この「私性」のところに、神たる所以があるけれども、それ以外は、まったく100%人間だということです。一つの受精卵――まあ、いわゆる処女懐胎ということをキリスト教は信じていますから、[キリストは]特別って言うんですけれど――、まったく人間の細胞としてお生まれになった。でも、その「私性」、つまり「イエス・キリスト性」というのは、神性、神である。その神が、人間と同じように大きくなっていかれる。
ということで見ていくと(中略)、つまり、本当にこれはヴィパッサナーをしていて分かるようになったんですが、十字架上のイエスの苦しみは、100%人間としての苦しみである。でも、その苦しみから、神としてのキリストは離脱しているという。はい、ものすごい、ちょっと神秘的なところなんですが。
でも、最初のほうに言いました、「自分の激しい脚の痛みであるのに、ふと気がつくと、まったく巻き込まれないで穏やかに、その痛みという現象を自分のこととして受けとめられる」というのは、もう一人の私ですね。あるいは、真の私がそのように気づけていると、その真の私は、私の身体的な痛みに巻き込まれていない。こういうふうな現実が出てくる。
つまり、こういうふうに見ていくならば、「私たちが神の似姿として造られているのは、このイエス・キリストのキリスト性という、無なる神という場に、実は私も与る身なんだ。一人ひとりは。というところに、神の似姿として造られた私たちの場がある」と。まあいわゆる、キリスト教の教えの枠の中ですけど、突き詰めていくと、こういう理解に到達することができるんじゃないか。まあ、あくまでも私なりの考えなんですが。でもこれは、こういうふうな瞑想修行とものすごく重なってくるということですね。
そうしていくと、今まで[の]「痛い、痛い。何とかしなければ」というエゴが本当の私ではなく、それを静かに、無償・無条件の存在受容として認めることができる、もう一人の私、真の無なる自己というところに本当の私があり、その無なる自己こそが神との接点になっていく。そこで私は、神の似姿として造られた、その私に目覚めて現実世界を生きることができる。巻き込まれそうになりながらも、静かに見つめる心を持って、全く穏やかな自由な心で。そして、そここそが、全く無理なく自然体で、一切条件を持ち込まずに、アガペの愛を生きられる場です。「無」だからです。そしてその「無」は、神によって満たされているから、それ以上私は何も必要としない。そこに本当の幸せがある。そこに本当の平和もある。こういうことではないかと、だんだんと気づき始めました。
まあこれは、良道さんとのやりとりを通して色々と私なりに、「自分が信じているキリスト教の中心とは何か」というふうな、そういったところも、だんだんと気づかされていく中で、今のところ私が到達した地点だということです。
一応、キリスト教の枠の中でお話しましたけれども、これを少しですね、置き換えると、もう色んな枠でですね、これを私たちはまた自分のこととして見ていくことができるのではないか。そして、丁寧に見ていくならば、本来の私は、もう最初から「もう一人の私」なんです。でもそれに、やっぱり気づかない、目覚めない、という中で生きているから、いわゆる「映画の中の私」として生きちゃってる。でもそうではない。そこに本当の私は無いということですね。
時間が来ましたので、これぐらいで終えたいと思います。一つの参考にして下さればと思います。
(終わり)